最新号
道路行政セミナー・12月号
ROAD ADMINISTRATION SEMINAR・2025 Dec
令和7年12月25日発行
INDEX
TOPICS
主要地方道鞆松永線 鞆未来トンネルの開通について
・・・広島県 土木建築局 道路整備課
地域における道路行政に関する取組み事例
- 出張所のDX化に向けた取り組み
~ 3次元道路管理情報システムの構築と運用 ~
・・・国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所 管理第2課 - 長野県における新技術を用いた道路パトロール業務の効率化と舗装点検への活用事例
・・・長野県 建設部 道路管理課 - 鉄道廃線跡地(長野電鉄屋代線)を活用した自転車歩行者専用道の整備について
・・・長野県 千曲市 建設部 道路河川課 建設係
TOPICS
主要地方道鞆松永線 鞆未来トンネルの開通について(PDF:1,128KB)
広島県 土木建築局 道路整備課
Point
瀬戸内海を代表する景勝地の一つである「鞆の浦」の町なかを走る主要地方道鞆松永線は、道幅が狭く慢性的な交通混雑が生じており、住民の生活や安全に影響が生じていました。このような交通課題解消のため、令和7年3月に「鞆未来トンネル」が開通しましたので、これまでの経緯や取り組みについてご紹介します。
地域における道路行政に関する取組み事例
出張所のDX化に向けた取り組み
~ 3次元道路管理情報システムの構築と運用 ~(PDF:464KB)
国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所 管理第2課
Point
岡山国道事務所では、道路管理の効率化・高度化を目的に、玉島維持出張所の執務室内で直感的かつ立体的に施設状況を把握できるよう、3次元の道路施設情報を活用した「3次元道路管理情報システム」の開発に取り組んだ。本稿では、当システムの構築方針と機能構成、更に道路パトロールカーの360度映像取得の活用状況について紹介する。
長野県における新技術を用いた道路パトロール業務の効率化と舗装点検への活用事例(PDF:1,094KB)
長野県 建設部 道路管理課
Point
長野県は、約5,200kmと日本有数の道路管理延長を持ち、道路パトロールによる日常管理などを実施しているが、老朽化の進行や技術者不足などが問題となっています。そこで、安全で円滑な交通の確保および道路施設の維持管理の効率化を目的に、道路パトロールと舗装点検を支援する新技術を導入しました。新技術導入によるパトロール業務の効率化および舗装点検へのデータ活用事例を紹介します。
鉄道廃線跡地(長野電鉄屋代線)を活用した自転車歩行者専用道の整備について(PDF:3,431KB)
長野県 千曲市 建設部 道路河川課 建設係
Point
旧長野電鉄屋代線は平成24年4月に廃線となり、平成25年12月に長野電鉄㈱から本市を含む沿線自治体(千曲市、長野市、須坂市)へ一括無償譲渡されました。本市へは延長約4.2kmの廃線敷が譲渡されており、現在自転車歩行者専用道の整備を進めています。
本稿ではその事業概要についてご紹介します。
編集後記
日の出から日の入りまでの時間が、最も短くなる日を冬至といいます。今年は12月22日でした。地域によって異なる部分もあると思いますが、冬至には、南瓜(なんきん/かぼちゃ)を食し、ゆず湯に浸かるという風習があります。
南瓜は、夏の野菜ではありますが、長期保存することができ、ビタミンが豊富であることから、冬の大切な栄養源であったそうです。また、病気除けの民間信仰のほか、名前に「ん」が付くことから、運が良くなるという江戸文化の洒落で、縁起を担いでいたといわれています。そのほか、南瓜は黄色いことから、陽の色といわれていることも所以のひとつのようです。
ゆず湯については、この先、融通(ゆうずう)がきくようにという言葉遊び文化の中で生まれた縁起担ぎのほか、香りの強いゆずで邪気を祓い、身体を温めて健康を守るという生活の知恵が合わさり、冬至の風習となったそうです。夜明けが遅い冬の朝は、冷え込んだ空気の中で朝日がひときわ鮮やかに映え、澄んだ空気とともに、身が引き締まる感覚を覚えますが、冬至を過ぎると、陽が少しずつ伸びていきます。このことから、古の人々は、太陽が力を取り戻していく日であると考え、運気が底打ちをして上向きに転じるタイミングであり、冬至を境に、良い運気に恵まれると信じてきました。
例年、冬至を迎える年末から年始にかけ、不思議と縁起を担ぎたくなり、この年末には、冬至から節分までに間に頒布される金銀融通のお守りを授けていただきに参りました。警察官や警備員の誘導が必要なほどの大混雑で、長く受け継がれてきた信仰の篤さを感じました。また、この1年を通じても、パワースポットと呼ばれる縁起の良い場所に足を運びました。パワースポットとは、科学的には証明されていないものの、訪れると身体が元気になった感じがするとか、心が落ち着くといった場所とされており、こうした感覚が生まれる背景には、長い間信仰の対象となってきたことや、山や谷、森や滝といった自然環境などが関係しているようです。本年は、行きたいと思っていたパワースポットを3か所ほど巡ることができました。その甲斐もあり、良き巡り合わせに恵まれ、笑いの多い、健やかな時間を過ごすことができました。そして、来年も良い1年であったと振り返ることができますよう願いを込め、本年の結びとしたく存じます。来年も、どうぞよろしくお願いします。(U)
お問合せ窓口
(一財)道路新産業開発機構 松澤
TEL:03-5843-2911 Mail:RAseminar@hido.or.jp
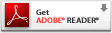
PDFファイルをご覧いただくためにはAdobe Readerが必要です。
Adobe社のウェブサイトより無料でダウンロード可能です。