最新号
道路行政セミナー・6月号
ROAD ADMINISTRATION SEMINAR・2025 Jun
令和7年6月30日発行
INDEX
道路占用Q&A
バス停留所標識に添架する広告物について
・・・国土交通省 道路局 路政課 道路利用調整室
TOPICS
都市計画道路戸畑枝光線・北九州高速5号線「牧山~枝光間」令和7年3月1日に開通しました
・・・北九州市 都市整備局 街路課
地域における道路行政に関する取組み事例
- つながる中部42.6の取り組みについて
・・・中部地方整備局 道路部 道路計画課 - 秋田県におけるDXを活用した道路維持管理に係る取組みについて
・・・秋田県 建設部 道路課 - 「群マネ」モデル都市「おおだて」の暮らしを支える「道路等包括管理」の取組み
・・・秋田県 大館市 建設部 土木課
道路占用Q&A
バス停留所標識に添架する広告物について(PDF:143KB)
国土交通省 道路局 路政課 道路利用調整室
Point
バス停留所標識に添架する広告物について解説する。
TOPICS
都市計画道路戸畑枝光線・北九州高速5号線「牧山~枝光間」令和7年3月1日に開通しました(PDF:5,377KB)
北九州市 都市整備局 街路課
Point
環状放射型の自動車専用道路ネットワークの一部を担う「戸畑枝光線(全長5.2km)」。平成23年度から14年の歳月をかけて、牧山から枝光までの区間(延長2.7km)が令和7年3月1日に開通しました。本稿では、北九州市の街路事業と福岡北九州高速道路公社の有料道路事業との合併施行方式で整備を進めている「都市計画道路戸畑枝光線・北九州高速5号線の整備」及び「同線牧山枝光間の開通」について紹介します。
地域における道路行政に関する取組み事例
つながる中部42.6の取り組みについて(PDF:1,512KB)
中部地方整備局 道路部 道路計画課
Point
中部地方整備局では、令和6年度末から令和7年8月末までに4事業6区間、総延長42.6キロにおよぶ新たな道路ネットワークが誕生する予定だ。開通にあたっての機運醸成のために「つながる中部42.6」と銘打ち、各事業の整備効果や開通に向けての進捗状況などを積極的にPRするために取り組んだ全体広報について、紹介する。
秋田県におけるDXを活用した道路維持管理に係る取組みについて(PDF:2,174KB)
秋田県 建設部 道路課
Point
秋田県では、他県に先駆けて人口減少が進行しており、建設業の担い手不足や土木系公務員の減少などの問題に直面しています。
このような状況下においても、将来にわたり適切なサービスレベルを維持するためには、効率的な道路維持管理が欠かせませんが、広い県土に多くの道路施設を有する本県では、現場と地域振興局(出先機関)が遠く離れている場合、異常箇所の状況把握に時間を要することに加えて、情報共有の円滑化や迅速な対応に関して、多くの課題に苦慮している状況となっていました。
本稿では、これらの課題を解決し、より効率的かつ高度な道路維持管理を実現するために導入した道路管理システムの概要をご紹介します。
「群マネ」モデル都市「おおだて」の暮らしを支える「道路等包括管理」の取組み(PDF:2,452KB)
秋田県 大館市 建設部 土木課
Point
北東北の中心(内陸部)に位置する大館市は、道路や河川、公園などインフラの「包括的民間委託」へかねてより取組んできました。北国の地方都市が抱える「人手不足・老朽インフラ増大」の課題を直視し、「多分野横断」を基軸に、「人口減少化社会であっても幸せを導くまち」を目指している現状をご紹介します。
編集後記
梅雨入りが発表されたものの梅雨前線が消えてしまい、早くも梅雨明けするような報道もありましたが、なんとか梅雨前線が復活し、梅雨空が戻ってまいりました。
梅雨の時期は、湿度が上昇するとともに、梅雨前線に沿って低気圧が頻繁に通過し、気圧が低い状態が続くことで、身体の不調に悩む人が多い季節です。湿度が高いと体温調節のための発汗がうまく機能しなくなること、また、熱が体内にこもりやすくなることで、身体がだるく、疲労感を覚えることがあります。そして、気圧が低い状態のもとでは、血管が拡張しやすくなり、この血管の拡張が神経を圧迫して、頭痛やめまいといった症状に見舞われることが増えます。
この時期特有のだるさや疲労感には、身体にたまりやすくなった水分の排出を促す食材を取り入れることで、改善されるといいます。体内にこもった水分を出す手助けをしてくれるカリウムを豊富に含むキュウリやスイカなどが、日々の食事に取り入れやすい食材です。きゅうりのお漬物やスイカは好物なので、積極的に取り入れることができそうです。他には、漢方で「利水(滞っている水を身体全体に流し水分の循環を良くする)」に使われる代表的な食材である、はと麦や小豆が良いとされているようですが、日常的に取り入れるには少しハードルの高さを感じます。
頭痛やめまいといった症状には、血行を良くして、身体の冷えを和らげることが有効です。血行を促進し身体を温める食材としては、ショウガが良いようです。わたしは、暑くてもさっぱりと食せるお豆腐に、すりおろしたショウガをのせています。そうめんなどを食す時の麺つゆに入れても美味しいです。また、血液をサラサラにしてくれる硫化アリルを含み、頭痛緩和にも効果的なものとしては、タマネギやニンニク。すりおろしたり炒めたりすれば比較的容易に取り入れることができそうです。気温も湿度も高まってきている今日この頃。家の近くに、手ごろな価格で美味しいアイスクリームが買えるお店が開店し、結構な頻度で通ってしまっています。甘く冷たい食品は、身体に水分をため込みやすく、胃腸を冷やしてその働きを弱めてしまうため、血行促進を阻害する要因となるそうで、身体の不調を改善すべく取り入れた食材の効用が消えてしまいます。暑くなったからといって冷たいものを求めすぎることに、注意していきたいと思います。(U)
お問合せ窓口
(一財)道路新産業開発機構 松澤
TEL:03-5843-2911 Mail:RAseminar@hido.or.jp
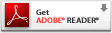
PDFファイルをご覧いただくためにはAdobe Readerが必要です。
Adobe社のウェブサイトより無料でダウンロード可能です。